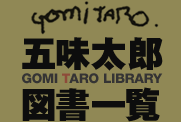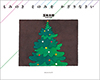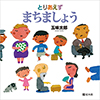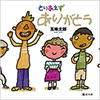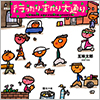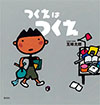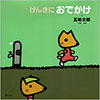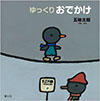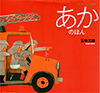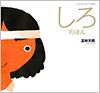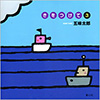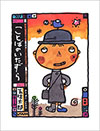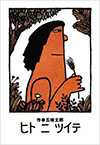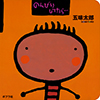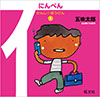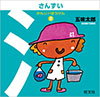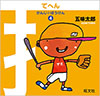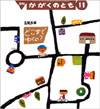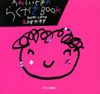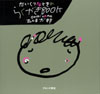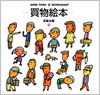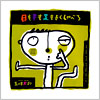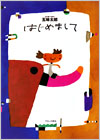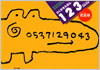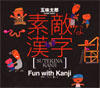![]()
2025年06
月
ならしている
「ならんでいる」の語呂合わせでとりあえず「ならしている」のですが、とんでもなくうるさい愉快な絵本になりました。ならすのがキリなく楽しくなってきて、皆さん総出でならしてもらったのですが、その結果、あ、僕もチェロ弾いていたのではなく、ならしていたんだ!と気がついてとても気楽になりました。そしてならしているうちに、ふっと奏でているようになったら上出来です。
2024年09
月
りょこうにいこう!
旅行に行くのは楽しいことです。どこに行くにしろ、誰と行くにしろ、旅行に行くのがいいのです。そして、旅行から帰ってくるというのが、またいいのです。そんな気分の絵本、行ってきまーす。行ってらっしゃーい。
2024年07
月
ならんでいる
なぜか突然、なんでもいいから並んでいる絵が描きたくなったのさ。理由はまったくわからない。で、とりあえず並んでいるゾウを描いた。イマイチ。次に自動車を並べて描いた。うーん。で、ペンギンみたいなのを並べてみた。あ、なんだかこれいい、と思ったらストーリーが自然にできた。これでいきます、でもペンギンたくさん描くのけっこうたいへんだ!と言うことでした。
2024年02
月
ぼくはふね
周りが画業50周年などとうるさく言うので、少しは気になったのかも知れません。人生なんてものを「ふね」に託してやや風景的な絵本にしてみたわけです。とはいえやはり絵本です。その人生観もまあ客観的です。いや、かなり主観的なのかな、そのあたりの判断はいつものように皆さんにお任せするわけです。いつものごとく、よろしくお願い申し上げます。
2023年02
月
とんでやすんでかんがえて…
考えるべき時にはいろいろと考えて、うん、今はやらない、時が来るまで待とう、なんて言う自己判断はなかなかいいものだと、描いた当人が改めて納得したのでした。ま、そんな気分の絵本です。一度読んでいただけたら幸いです。
2022年10
月
じぶんがみえない
子どものころからずーっと気になっていたことなのだけど、とりあえず僕は今絵本作家なのだから、一度は絵本に描いてみるべきなんじゃないかな、などと思って描いてみたのですが、でもやっぱり何も答えは見出せず、一生気にして生きていくのだな、と改めて思った次第です。
2022年7
月
めをさませ
この絵本が出来上がって、いつものように嬉しく読んでましたが、5、6回読み返しているうちにふっと、このチビのフクロウ、寝ぼけて落ちたんじゃないのかもしれない、と思いました。みんなをハラハラさせる墜落遊びをいつもしているんじゃないかと。だからお月さんもお家さんも一応お付き合いして「あら、まあ」なんてやってくれているんじゃないかと。
描く前には少しも気付かなかった、つまりコウモリやお星さんの気分でした。今度チビに会ったら本当のところはどうなの?って聞いてみます。
2022年3
月
JAZZ SONG BOOK
30年前に出版した同名の本のリデザイン復刻版です。古き良き時代のJazzの名歌曲を、訳詞とイラストでまとめたの仕事です。ついでに新たに5点ほどジークレー印刷の額装版も制作しましたので、チャンスがありましたらご覧になってください。よろしく。
2022年2
月
6Bの鉛筆で書く
久しぶりのエッセイです。コロナ禍の静かな暮らしのなかで、のんびりと書きました。海外旅行がとくにしにくい時期だったので、この20年間の旅で撮った写真をセレクトして使いました。楽しい作業でした。エッセイともども写真もお楽しみください。
2022年2
月
うるさいぞ… / こどものとも 年少版
描いた自分がビックリしてしまったので、これはたぶん傑作なのではないかと思います。いや、ビックリするのは初めっから分かっていたのですから、駄作かもしれません。いずれにしても、一度お読みになって下さい。よろしく。
2021年10
月
2021年3
月
まだまだ まだまだ
テニスとか麻雀とか旅行とか、もう十分遊んでそろそろおしまいという段になって、いや、もうちょっと、もう少し、まだまだ続けていたいなあなんていう気分がよくあります。体力的にはもうヘトヘトなんですけどね。で、そんな気分を絵本にしてみたらこんな具合になりました。で、ここは潔くおしまーい!にしてみましたが、やっぱり気分はまだまだ、まだまだです。絵本制作の場合も同じなんです。やれやれ。
2020年10
月
もみのき そのみを かざりなさい
3回目の再版新装版です。不思議なことにどんどん良くなります。誰が誰に言っているのかよくわからない命令口調が、なんとも快い。とりあえず「えほんを ゆっくり よみなさい」ということです。
2020年9
月
とりあえず まちましょう
なんだかいつも忙しくて、バタバタ、ウロウロ、イライラしているみなさん、ここはひとつのんびり、ゆったり、ぼんやりと、焦らず待ってみるのもけっこういいものですよ、というあたりで、とりあえず まちましょう、です。 すぐにお読みにならなくても構いません。 いつかお読みいただきたいと思います。お待ちしています。
2020年3
月
とりあえず ありがとう
少し理屈っぽく言うと「ありがとう」のもとは「有難い」ですから、有るのが難しい、そう簡単に起こる状況ではない、と言うわけですから、あまり気安く「ありがとう!ありがとう!」なんて使ってはいけない言葉なのですよ、と言うあたりのことを、ま、読んでお分かりいただけたら、とりあえず ありがとう! と言うことです。よろしくお願いします。
2019年10
月
絵本 むかし話ですよ 弐
「むかし話ですよ 1」がたいへん好評だった、ということにして、その2を描きました。少し読み物風になりました。「むかし話」という一見たわい無さそうに思えるものに含まれる悪意、あるいは毒のような気配が、昔から気になっていたので2冊も描くことになったけど、ようやく少しさっぱりしたのでした。
2019年9
月
きみののぞみはなんですか?
ちょっと変わった造本です。これに近い外国製の本を見つけて、こんな体裁の絵本を作ってみたくなりました。試しの束見本を見ているうちに、ごく自然に絵本が出来上がりました。僕の のぞみは 絵本を作りたい ということなんですね。やっぱり。どうやら。
2019年5
月
とりあえず ごめんなさい
とくに失敗したわけでもないんですけど、
とくに悪気があるわけでもないんですけど、
なぜかとりあえず、ごめんなさいをしておいたほうがよさそうなこと、この世には多々あるものでして、ま、それがなかなか味わい深いのですよね、って言うような絵本です。
とりあえず、お詫びかたがた、お楽しみください。
2018年7
月
CUT AND CUT!キッターであそぼう!
カッターで遊んでみましたらこれがけっこう面白いのでこんな本を作りました。ぼくのカッター遊び作品集といった趣です。
遊んでいるうちにカッターはともかく、切る紙についてもやや興味が湧いてきたので色紙の本も作りたくなり、ついでに、これは是非とも必要だと思ったのでカッターマットもデザインしました。完璧です。もちろん新発売の超安全カッターもカッタースタンドも完璧で、ついでに万が一を考えてそれでも指先を怪我したときのために絆創膏も入れようと提案したのですが、編集長に却下されました。
本と色紙の本だけの別売りヴァージョンもありますよ。
2018年7
月
行ったり来たり大通り
行ったり来たりはいつものことですが、それが大通りになるとは思いませんでした。
大通りではいろんなことが時空を超えて起こっているのですが、そのひとつひとつにスポットを当てれば、それだけでまた一冊の絵本になってしまいそうで、もうキリがありません。
うん、キリなく行ったり来たりしている間に、絵本館は40周年を迎えました。
キリなくめでたいことです。
絵本館のスタッフみんなにお祝いを。
2018年6
月
つくえはつくえ
しばらく前までは大きな机5台で仕事をしていました。いまは1台半です。落ち着いて来たのね。僕にとって机は生活そのもので、だからこんな絵本を描いたのかもしれませんが、机の上で机の絵本を描いるなんて、ま、気楽なもんです。気楽に読んでやって下さい。
2018年4
月
ひよこは にげます / こどものとも 年少版
「きんぎょが にげた」からずっと「にげる」ということを意識していたようで、この絵本を描いて改めて「にげる」ことの価値、意義を再確認したのでした。それがどんな再確認なのかは、ま、いちどお読みになってください。
2018年1
月
わたしとわたし / かがくのとも
「もうひとりの自分」について絵本的に考察してみたわけですが、描きながらつくづく、さらにもうひとりの、さらに次のもうひとりの自分に出会うわけで、あんがい深い本なのかもしれません。いや、そんなこと当たり前のことですから、かなり浅いのかもね。そこの判断がつきかねるところが、ま、この本のいいところなんであります…
2017年6
月
絵本 むかし話ですよ
腹が立ってもあきれても、そこはとりあえず大目に見てやってくださいな、何はともあれ昔話のことですからさ、なんて気楽にやってたら、おお、昔話は今話ではないか!と相成った次第で、昔話もけっこうやるもんだなあ、と言うことです。
2017年5
月
なんでもできる
「できることなら なんでもできる」とか「できないことは やっぱりできない?」とか「いや、できないことでも 時と場合によってはできることもある?!」ってなあたりがこの本のテーマであります。何故か突然こんな絵本を描いてみました。
2017年3
月
2017年2
月
2016年10
月
ゆっくりおでかけ
「おでかけシリーズ」の一冊目。2017年はじめにはNo.2、No.3が出る予定。毎日お出かけする人はわかりませんが、 僕のように時々しかお出かけしない人には「おでかけ」はかなりスリリングなものなので、その辺りをお楽しみください。
2016年9
月
勉強しなければ だいじょうぶ 改訂版
出版元、装丁、さらに中身も少し加筆訂正した新装再発行版です。つまりますます面白くなったと言うことで、ますます勉強しなければだいじょうぶ、という訳です。
2016年8
月
五味太郎 絵本図録
優秀なスタッフがこんな図録をまとめてくれました。これはいい図録です。なぜなら、五味太郎のこれまでの仕事の全貌がこれ一冊ですっかりわかる!と僕自身が感動したのですからね。
2015年9
月
2015年6月
きをつけて1・2・3
「きをつけて」はとりあえず愛の表現である。愛する者への気配りの言葉である。そう言っておくとちょっと安心するのである、こちらが。かけられた方もちょっといい感じなのである。ところがこの世の中、気をつけるべきことが山ほどあるので、愛の言葉などとのんびりやっている場合ではないのである。ほんとうに「きをつけて」なのである。そこが「きをつけて」のむずかしいところであって、そのあたりの3部作です。
2015年4月
ことばのいたずら
ことばは生きものですから、とりあえずはたらいたり、さぼったり、活躍したり、なんでもなかったりするわけで、で、たまにはいたずらもするわけで、そこのところは、ま、ひとつ大目にみてやってください、ということです。
2015年3月
ヒト ニ ツイテ
35、6年前に描いた本があっちこっち旅をして再び出ました。だんだん版が大きくなるのはどういうことでしょう。内容は大きくはなっていません。 いや、 大きくなっているのかもしれない。若気の至りで「わかったようなこと」を描いてしまったのだけれど、まあそれもけっこういいんじゃないかなと改めて思う 次第です。
2014年12月
ぼんやりしてたら… / のんびりしてたら…
ぼんやりしてたりのんびりしているとこんな楽しいことになるよ、ぼんやりのんびりしてないとやっぱりダメね、と言う、ぼんやりのんびり礼賛絵本です。あ、いつもと同じですね。
2014年12月
百人一首ワンダーランド
「何となくやっている うちにだんだん盛り上がってくる」というのが僕の普通のやり方ですが、今回に関しては盛り上がり過ぎまし た。 で、僕にしては珍しい三部作箱入り一見豪華風書籍と相成りました。ま、それぞれ盛り上がっておりますので、どうぞお楽しみください。
2014年09月
かげのひこうき
そう言えばこれに似たような経験あったなあと、この絵本が出来上がってから気がつきました。どこかの国ののんびりとした空港でぼくの頭上を飛行機が飛んで行って、その陰に中に一瞬入ったのでした。その時はただおおっとなっただけなのですが、そんな記憶が何年後かに絵本になるわけですから人生のちょっとした経験も馬鹿にできません。それにしてもこのところ、帰りはどうすんだろう?絵本が多いね。
2014年04月
あるいてゆこう 新装版
※五味太郎のおさんぽえほん(1)
造本上の不備などについて検討をかさねていましたが、ここに新装版ということで作り直しました。さらに手に馴染むいい仕上がりになったと自負しております。皆様のご感想、ご意見を。どうぞよろしく。
2014年04月
あそんでゆこう 新装版
※五味太郎のおさんぽえほん(2)
2014年04月
さる・るるる・る
だいぶ前から突然遊びに来るさるがいて、その度にしょうがないからお茶したりメシ喰わせてやったりしていたのだけど、何かの折にそのさるがこともあろうに「ぼくの絵本描ける?」などと言い出すので「そんなの訳ねえよ」と言ってしまったのが運のつき、ま,最初は適当に描いてやったのだけどこれが案外いい出来で、さる調子に乗ってもっと描けなどとうるさいものだからついでにもう少し描いてやって、そのまま放っておいたらしばらくはよかったのだけど、またこのところ頻繁にやって来るようになって、「最近のぼくはどうかな?」なんてまた始めたので「最近も将来もおまえのことなんかもう描かないぜ」とかわしたら「ほう...なるほど...」などとちょっと含んだ言い方するんで、あ、こいつ、描かないんじゃない!描けないって言ってるんだと思われてしまったんじゃないかと少しムカッとしたので、描けねえんじゃねえ,描かねえんだ,描こうと思ったらそんなの簡単さと言うところを見せてやるべえと,ま,やっぱり適当に描いた訳だけど、これがまた案外いい出来なのでなるべくさるには見せないようにするつもりである。
2014年03月
あっ・ほっ
あっとおどろいたりほっと安心したりの繰り返しが人生なんだなあとつくづく思う今日このごろであります。 「あ・ん」が人生だなどと言う偉いお坊様もいるらしいけれど、僕はなんと言おうと「あ・ほ」だと思うよ。 それを少し元気に「あっ・ほっ」とやっているあたりがいいんじゃないかと。
2014年02月10日
どこまでゆくの? / 上製本
35~6年前、「みち」というタイトルで月刊誌『かがくのとも』に描いたのが、ぼくの絵本制作活動のスタートらしいのですが、その月刊誌がめでたく通算500号を迎えたので、あえてまた「みち」をテーマに描いてみようと思ったのでした。それにしても「みち」というテーマは限りなく魅力的です。
2014年02月10日
にているね!? / 上製本
この人何かに似ているなあ…ああ、電信柱だ…、とか、このうどんはなんとなくお正月みたいな雰囲気だなあ…なんていつもやっているので、うまといすの類似点絵本なんてまったくの楽勝なのですが、いざ描いてみたらその哲学的な気配にあらためてびっくりしました。馬鹿なイメージ遊びも捨てたものじゃない。
2013年10月
ぞうは どこへもいかない
一時の気の迷いとか浮き世の義理とか、ちょっと魅力的なお誘いとか現状打破の目論みとかとかとかで、それこそあっちこっちへ出掛けて行くわけですが、でも結局気が付いてみたら元の場所に戻って来てしまうものなのだなあってな思いがあって、こんな絵本になったのじゃないかと思います。拙著「ぞうは どこへいった?」の象とは関係ない別の象です。いや,関係あるのかな? 今のところちょっとわかりません。
2013年06月
ならびました / いました
こういう風景がいつも頭の中にあります。それがなにかのはずみで外にでます。絵本という形で出られれば最高です。で、いつも謎なのはその「なにかのはずみ」というやつです。長いこと絵本を描いていますが、いまだにそのはずみがどこから来るのか、あるいはどこにいるのかよくわかりません。わからなくても別にいいか…などとも思っています。
2013年04月
熟語博士の宇宙探検
たとえば「うろうろだらだらしているちっちゃい奴等」のことを「幼児」とまとめます。「あいつ等をなんとかしなくてはいかん」ということを「教育」とまとめます。それをあわせて「幼児教育」とまとめます。わーい、偉そうにまとまったね!ということです。熟語、ならびに四字熟語の効用です。まとめたわりには何もまとまらない、というところも熟語の効用です。お楽しみ下さい。
2013年03月15日
かんじのぼうけん
この本は、漢字を「部首」でまとめた本です。 初回は「にんべん」「さんずい」「きへん」「てへん」の4冊。 漢和辞典で、所属している漢字が多い4つの「部首」を取り上げました。 本文に掲載した漢字すべてに五味太郎さんのかわいいイラストとコメントがついていて、楽しみながら漢字の形や意味を知ることができるシリーズです。(編集担当より)
2012年2月
ぞうはどこへいった?
ぼんやりとラフスケッチなどをしているとき、いつの間にか「ぞう」みたいなものを描いていることが、僕たびたびあります。なんでですかね。クセかしら。ぞうがすごく好きなのかしら。そこのところはよく分りませんが、とりあえずぞうの絵本です。これもぼんやりスケッチしているうちに出来上がったものです。
2012年2月01日
ときどきの少年/文庫版
絵本にはときどき小型版というやつがあって、普通版はおうち用、小型版はお出かけ用なんてシャレた使い分けをしているガキもいるわけで、この文庫版もそん な感じになったらいいのにね、なんておもうわけです。普通版(ブロンズ新社)もよろしくね。この文庫版、椎名誠さんの解説が付いているので、そこのところ はお得です。
2011年12月20日
わざわざことわざ
もうすっかり飽きたはずの「ことわざ」を凝りもせずまたまた、わざわざやってるところをみると、僕本当にことわざ好きなんだなあと改めておもいます。ことわざ病なんでしょうな。なんなのでしょうね、この病は? で、そうは言っても今度の本がやっぱり一番おもしろい!と思っちゃうわけで、これもまた別の病気なのかしらね。こっちは慢性だな。「同病相哀れむ」のこころでひとつよろしくお願いします。
2011年9月25日
らくがきむすめとおともだち
いつのまにか世界的になってしまった「らくがき絵本」シリーズ、ヴァリエイションも数冊出ましたが、これが最後です。「いいところはお客さんに描かせてあげる」というサーヴィス精神が裏目に出て、だいぶフラストレーションが溜まりましたので、最後のらくがき絵本は全部僕が描いちゃいました。めでたいめでたい。
2011年8月
なんとなく
「なんだ?『なんとなく…』だと! 馬鹿を言ってんじゃねえ、そんないい加減なことで人生やっていけるわけねーんだよ」 なんて言うおじさんとか、「もっと計画的、戦略的、段階的にしっかりとやらないといけませんことよ」などとおっしゃるおばさんがたに、この絵本を捧げます。なんとなくしっかりと描きました。
2011年6月1日
世界は気になることばかり
まさにタイトル通りの今日このごろであります。なにしろ世の中、気になることが多くて、それが僕の場合、まことに楽しいのですが、少し不安でもあるわけです。つまり不安もまた楽しからずや、ということね。
2011年4月1日
にているね!?
この人何かに似ているなあ…ああ、電信柱だ…、とか、このうどんはなんとなくお正月みたいな雰囲気だなあ…なんていつもやっているので、うまといすの類似点絵本なんてまったくの楽勝なのですが、いざ描いてみたらその哲学的な気配にあらためてびっくりしました。馬鹿なイメージ遊びも捨てたものじゃない。
2011年2月
ぐりぐりくん
とりあえず、ぐりぐりくんですが。この人は誰なんでしょう。たぶん、いい人にはちがいないんですが。あなたの周りにこんな人います? もしかすると、この人は人ではないのかもしれません。人の部分かもしれません。描いたあとでも作者自身もよくわからない本は、たぶん傑作です。
2011年01月01日
砂漠と鼠とあんかけ蕎麦
神さまについての話
そもそも宗教を携えてきた人間というものに興味がありまして、宗教学者・山折哲雄先生と約30時間にわたって神さまについて語り合った人生初の対談集です。山折先生は「あんかけ蕎麦」、俺は「天せいろ」を食べながら語り合ったこともあって、このようなタイトルになりましたが、中身はかなり濃い味です。
2010年11月1日
どこまでゆくの?
35~6年前、「みち」というタイトルで月刊誌『かがくのとも』に描いたのが、ぼくの絵本制作活動のスタートらしいのですが、その月刊誌がめでたく通算500号を迎えたので、あえてまた「みち」をテーマに描いてみようと思ったのでした。それにしても「みち」というテーマは限りなく魅力的です。
2010年08月25日
らくがきBOOK
どうやら20年なんだそうです。何が? 「らくがき絵本」という変な本を作ってから、20年たったらしいのです。 つまり20年前にそんな本を作って、気がついたら十数カ国版に翻訳出版されていて、今もなんとか続いているというわけです。めでたいことです。で、その記念というかついでというかで、また新しい「らくがき絵本」を作りましたよ。4冊セットです。お好きな方はまたまたらくがきして下さい。まだまだらくがきして下さい。
2010年04月30日
勉強しなければだいじょうぶ
久しぶりの学習論です。今回は、「勉強」と「学習」の本質的な差を探ってみました。で、結論は、「勉強しなければだいじょうぶ」ということになりました。つくづく名言だと思います。
2010年04月25日
買物絵本
人生において“買物”が山場です。いろんな意味において……。買いたいもの、買うべきもの、買わされたもの、買うしかないもの、買ってはいけないもの、などなどをめぐる絵本です。だいぶ前に描いた本を、時代の要請にお応えしてリニューアルしました。買うべき本です。
2010年03月25日
挨拶絵本
人生において“挨拶”が山場です。この場合は、人生のあらゆる関係性において挨拶がどう機能するかを考察した絵本です。この本を、どうぞよろしくお願い申し上げます。……というのも挨拶のひとつです。時代の要請にお応えした新バージョンです。
2010年02月25日
質問絵本
僕は質問が好きです。子どもの頃からやや質問魔と言われていました。深く考えないですぐ聞きます。質問してから考えます。「これなあに?」「これいくら?」「これ売れるの?」「どういう人が買うの?」……お店の人が「余計なお世話だ」とか、嫌われることもありますけれど、けっこう楽しいです。で、答がその人の人格です。この原理原則を絵本にしたのが『質問絵本』です。だいぶ前に描いた本のなぜかリニューアルです。質問し続けろということでしょう。
2010年02月25日
目も手も足もよくしゃべる
身体の部分を介した表現はとても魅力的です。身近な表現なので分かりやすく「目に浮かぶ」し「腑に落ちる」。そんな日本語独特の、この風土独特の表現をやや客観的に味わってみようと思い、あえて英訳も試みました(これはマイケル君が頭をひねりました)。『すてきなひらがな』『カタカナ』『漢字』に続く“すてきな身体表現”といったところです。お楽しみください。
2010年01月01日
はじめまして
描き終って出版したあとから「ああ、なるほど、こんな感じのことをぼくはときどき考えていたんだね、ふうん、なるほどね、ああ、そうなんだよね、でもさ……」なんて思うことがよくあるのですが、そういった絵本、わりといいです。ぼくにとって、わりといいです。皆さんにもちょっといいと、いいんですけど。
2009年05月01日
四字熟語グラフィティ
この「四字熟語グラフィティ」は「正真正銘」の傑作、「前代未聞」の名著、こんな本に出会えるのはまさに「一期一会」、楽しみながら知恵がつくところは「一石二鳥」、家族みんなで読めば「家庭円満」、子供の知性感性を「切磋琢磨」、今手に入れるのが「先見之明」、などと勝手なことを言うのを「自画自賛」あるいは「我田引水」と言います。ようするにそんな具合の本です。どうぞよろしく。
2009年02月01日
その気になった!
その気になって描いていたら「な、なんだ、これ俺のことじゃねえか!まいったなあ」と気が付いたのでした。
で、このエンディング、なかなかいいです。はっとしました。
そうだよなあ、俺もなるべくこんな気合いでこれから頑張ろう!と改めて思ったのでした。
自分の絵本は自分に一番役立ちます。
2009年01月01日
かけまーす どん
北京オリンピックのマラソン中継をTVでぼんやり見ていて、先頭のアフリカ人が北京大学の構内を疾走しているあたりで突然「あ、走ってる絵本描こう!」と思ったのさ。
で、こういう絵本になりました。
この子、ケニア人が乗り移っているのよ。速いよ。
2008年12月25日
らくがきえほん1・2・3(完全版)
とりあえず、数字を楽しむことに特化したらくがきえほんですが、「らくがきは、ぶ厚いのが素敵!」ということで、しばらく前に出版したものを、書き足しリメークしました。「完全版」とふってあるのは、そういう意味です。とくに外国人は単純なので厚いと喜ぶという傾向があります。さらに、黄色い本は売れるという傾向もありがちなので、表紙デザインを一新しました。そろそろ外国からのオファーもありそうです。乞う期待!
2008年06月16日
素敵な漢字
『すてきなひらがな』『ステキナカタカナ』につづく第3弾は予想通り『素敵な漢字』です。といっても「かな」48文字に比べてこの漢字はもう膨大な数量がありますので、おのずから「好きな漢字」に絞り込み、まずは毛筆で書きまくることから始めました。で、こんな本になりました、このシリーズはこの3冊で完結。
2008年05月07日
わかりますとも!
干支セトラシリーズ第12弾、つまりこれで完成です。めでたい。ほぼ3年半で12年ひとまわりを生きてしまったような気がします。で今年が何どしなのか、もうすっかりわからなくなってしまうほど干支づけでした。たまには「今年は干支は特になし」みたいな年があってもいいような気がします。ま、どうぞみなさま、よいお年を。
2008年03月19日
ぼくはぞうだ
1976年刊(福音館書店)の復刻版です。今あらためて読んでみると、なあんだ、俺は昔から「ぼくは 五味太郎だ」って言いたかったんだなあと少し呆れます。自意識過剰なんて雑な言葉で括ってしまうにはちょっと惜しい、創作とは所詮そういうもんだ!と括ってしまっても色気がないなあ、などといろいろ考えている訳です。
2008年03月03日
みんなのひつじさん
「虎」とか「午」とか「子」などには、それなりの関わりといいましょうか縁といいましょうか、なんらかのなじみがこの人生においてあったのですが、こと「未」に関してはそんなのぜんぜんなかったなあと、改めて気づいたのでした。で、少していねいに描きました。